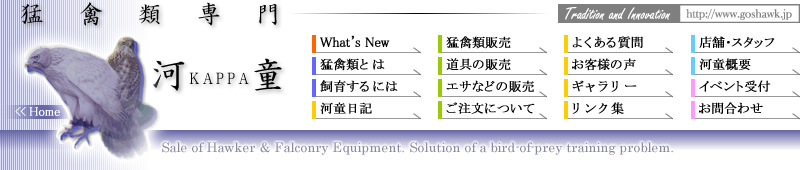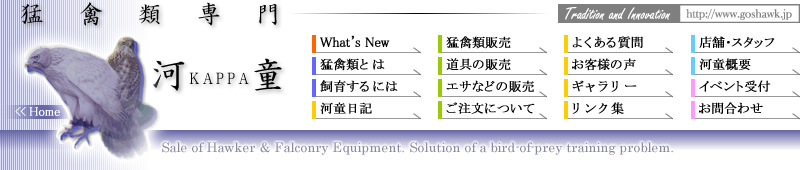2014/03/14 [No.3873]
2014/03/14 [No.3873]
和式の足革
現在、私達(意見はいろいろございましょうが・・・)は安全性の面から「あえて洋式!」のアンクレット&ジェス方式の足革を使い、一般には推奨しています。
NPO法人 日本放鷹協会では、諏訪流の伝承と言うことで、諏訪流に伝わる和式の足革を使うこともありますし、鷹匠は製作、取付け、使用ができなければなりません。
ちなみに流派により、形状違いがあったり、付け方の違いがあったりします。
だからと言うわけではありませんが・・・また、こだわるお客様達も居られるので注文などもあり、私自身は年に何組かは作ることになります。
まぁ、調教開始前の秋の注文、制作が多いのですが・・・
今回は「暇なときに作っといて!」と依頼があり、2組作りました。
今回のものは紫革、少しでも軽くする為に細めのタイプ、フィニッシュ系のGBスパなどへの対応で少し長めに作ってあります。
本来、宮内庁時代の道具は簡素で、革も燻し革です。
紫革は使いません。
江戸時代などは良い鷹、そこまででない鷹などで色は分けられていました。
紫革はツルを獲った鷹に付けることが許されたと聞いています。
まぁ、今は自由な時代ですので、好きな色で良いのですが、紫革は鷹の色と合っているというか、映える色で私は好きです。
|